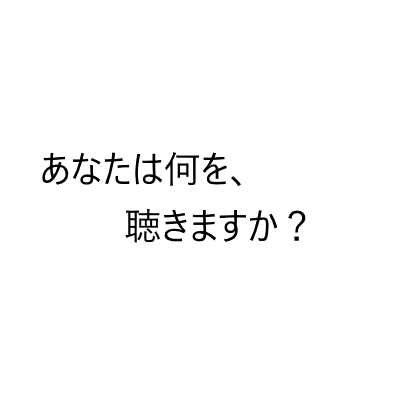今履修している授業のひとつに、「音楽美学」というものがあります。
毎回、ある作曲家にフォーカスした映像を視聴して、それをもとに(悪い面ではなく良い面に注目して)批評文を書くという内容です。
批評文は当日提出して、次の授業の冒頭で、数名のものが紹介されます。
人の批評文を読むというのが非常に気づきが多くて、サン=サーンスの回の内容については、私はなんと表層的な聞き方をしてしまったのだろうと反省しました。
そのときに題材となった作品は有名な『動物の謝肉祭』ではなく『』でした。批評文のタイトルの指定は「サン=サーンスの本音」。
私は、サン=サーンスが周囲の現代音楽作曲家たちに迎合することなく、あくまで調性を保ったまま大衆に受け入れられやすいと思われる形式の音楽を作り続けていたことから、人々に広く受け入れられる音楽が作りたいというところに本音があるのではないかと書きました。
ところが、次の授業で紹介された批評文では、サン=サーンスは自分の才能が認められないことに納得がいっていなかったというような、裏にある自己顕示欲のようなところまで踏み込んだ内容がありました。
それが正しいかどうかは分かりませんし、今回の批評文でそれを書くかどうかというのは個人の判断ですが、少なくとも、私はそこまで考えがおよんでいませんでした。書く書かないに関わらず、そこに考えが至らなかったのは、聞き方が浅かったなと言わざるを得ないと思います。
それ以降、というべきか、実際には最初からかもしれませんが、毎回この授業で提出する批評文の作成には非常に苦心しています。音楽的な知識を問われているわけではなく、あくまで自分の感性でしっかり考えて書けばよいことになっているのですが、どんなにしっかり聞いているつもりでも、それはつもりでしかないのだと実感することが多いです。
授業で見る映像は、演奏そのものであったり、オーケストラのリハーサル風景であったりと様々です。リハーサル風景は、曲を知り尽くした指揮者による解釈に触れることができるので、非常に勉強になります。
つい先日の授業の映像がまさにリハーサルのもので、曲はドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』だったのですが、途中で指揮者が発した一言、「老いた牧神だな。私が追い立てなければならない。」(ちょっと違ったかもしれませんが、このような内容。あるフレーズでテンポが重くなりがちなオケに対する言葉)というところでは面白い表現だなと思ったとともに、指揮者の頭の中にはこれだけ鮮明に曲の情景が浮かんでいるのだなと感心しました。